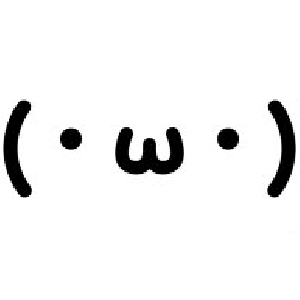古くから広い地域に伝わる民間伝承である。日本ではペロー版が有名である。日本を含め世界的に極めて著名な作品であり、オペラ・バレエ・映画・アニメなど様々な二次作品が多数作られている。

シェアする
Q.「おしん物語」は何に収められている?
西本教授
「1901年に冨山房から出た小学校の国語の教科書として、国語読本に収められている作品のひとつですね。」
その内容を現代の「シンデレラ」と比べてみると・・・
【補足トリビア】
①明治34年(1901年)に冨山房から出版された「国語読本高等科女子用」に収められている。
②日本人によりよく親しんでもらうために、作者の坪内逍遥がタイトルも中身も日本風にアレンジした。
③「シンデレラ」が苦難を耐え忍んでいるさまから、「おしん(お辛)」と名付けた。
④橋田壽賀子さん脚本のドラマ「おしん」とは全く関わりはない。
⑤「シンデレラ」がガラスの靴がぴったりなことで証明したのに対し、おしんは扇のガラを当てて証明した。
1900年に坪内逍遥が本名の坪内雄蔵名義で高等小学校の教科書用に「おしん物語」の題名で書いた際はシンデレラは苦難を堪え忍んでいる姿から名前を「おしん(お辛)」とされ、魔法使いは弁天、ガラスの靴は扇、王子は若殿、魔法の効力が切れるのは夕方6時、王子と会ったのがシンデレラだと証明した方法は扇の色を当てるなど和風にアレンジされた。
「シンデレラ」が載っているのは1900年(明治33年)の小学校の国語の教科書である。 坪内逍遥が本名の坪内雄蔵名義で教科書用に書いたもので、題名は「おしん物語」
日本で「シンデレラ」が伝わったのは、明治時代の頃で、一般的な書物ではなく、小学校の教科書「国語読本高等科女子用」に収められて、題名は「おしん物語」であった。
- 1