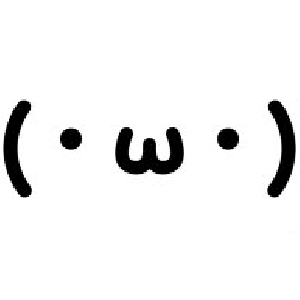歌唱またはメロディパート(主旋律)を担う楽器を演奏する際に、事前に制作された伴奏を再生して歌唱・演奏する行為をいう。

シェアする
実際に入れてみた。
曹洞宗桃源院の皆さん
「摩訶般若波羅蜜多心経 観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空~」
【補足トリビア】
①「般若心経」は正式には「摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみったしんぎょう)」。わずか266文字の短い経文のため広く親しまれ、法事などでは一番よく読まれるお経である。
②もともと家庭で活用してもらおうと家庭用カラオケに「般若心経」を入れたのが始まりで、通信用カラオケには「面白いかな」という理由で平成7年(1995)8月から配信を始めた。
カラオケのカラは「空」、オケは「オーケストラ」の略で、楽団・楽隊による生演奏ではなく、レコードやテープで代用することを指し、本来は放送業界で使われていた用語であった。
1985年、岡山県でトラックの運転手をしていた佐藤さんがコンテナを改装し、中にカラオケ機材を持ち込んだのが最初といわれている。
「Karaoke」は、日本語でも「カラオケ」と発音します。日本語で「カラオケ」の「カラ」は「中身がない」という意味で、「オケ」は「オーケストラ」の略で、放送業界で使われていた専門用語です。
- 1